仮閉鎖中です。
カウンター
アンケート
カレンダー
各企業様・出版社様・原作者様とは一切関係ありません。無断転載等はご遠慮下さい。
カテゴリー
プロフィール
HN:
莉葉
性別:
女性
自己紹介:
当ブログサイトはリンクフリーです。
よろしかったらどうぞ
http://setuna.blog.shinobi.jp/
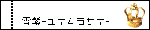
報告いただければ伺わせていただきます。ってか泣いて喜びます!
オンラインブックマークはご遠慮下さい。
当ブログサイトはリンクフリーです。
よろしかったらどうぞ
http://setuna.blog.shinobi.jp/
報告いただければ伺わせていただきます。ってか泣いて喜びます!
オンラインブックマークはご遠慮下さい。
最新トラックバック
ブログ内検索
アクセス解析
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
Fuji*Ryoma
目線が最近よく合うような気がする。
なんて、それはオレの気のせいなのかもしれないけれど。
恋とか、愛とか、そんなものじゃなくていいから、少しでも、少しだけでも、見ていてくれたら嬉しい、な。
Sweet colors
「好きです」
鈴のような可愛らしい声が人気の少ない、というより人気のない裏庭に響く。
此処が校内でも有名な告白スポットだなんて全く忘れていた。
そんな場所で、しかも死角になるような場所で昼寝をする自分も悪いが、回りを確認せずに告白劇をおっぱじめる彼女も悪い、と心の中で悪態をつく。
そんな一人の少女が頬を染めて一生懸命告白している相手は、自分のチームメイト兼先輩である甘栗色の髪と瞳を持つ笑顔を絶やさない『彼』だった。
告白を受けている今も微笑みを保ち続けている。
が、面倒くさいと言うのがありありと見て取れるほど今の彼を纏う空気が違うのだ。
彼らしくもない、どうかしたのだろうか。
そんな微妙にしか違わない彼の雰囲気を感じ取れるものなど殆どいないだろう。
大抵の者はあの笑顔に騙されるから。
それほど些細なものなのに、それに気づいてしまった自分がどれだけ彼を見ているのか再び認識させられる。
どれだけ見ていたって、どれだけ想っていたって、彼が振り向いてくれるだろう事はありえないというのに…。
馬鹿みたいだな、と思っていると甘栗色の彼が口を開いた。
「…ごめんね、僕は君の気持ちに応えてあげられない」
冷たい声だと思った。
表情は笑顔のままだったけれど、突き放すような、そんな、冷たい音だった。
「好きな人がいるんだ」
続けられた言葉に、自分に言われたわけではないというのに心に深く何かが突き刺さったような気がした。
その声は今までの中でも一番甘く響いていて。
その表情も比べ物にならないくらい甘くて切ないものだった。
本当に好きなんだ、と知りもしない彼の想い人に嫉妬の感情を覚える。
オレにはそんな権利ありはしないというのに。
自分の考えに没頭しすぎて、周りの状況がつかめていなかった。
だから、近づいてくる足音に気づけなかったのも仕方のないことだった。
「…覗きは良くないなぁ」
「…っ」
その声に慌てて振り向くと目の前に広がったのは甘栗色。
オレの想い人だった。
「ふっ…不二先輩っ!別に見たくて見てたわけじゃありません!」
本当に、見たくも聴きたくもなかったんだ。
顔を歪めてそう言うオレに不二先輩は小さくため息を吐いた。
そのため息に肩を揺らすオレに不二先輩は苦笑すると口を開いた。
「…越前、おおかたお昼寝でもしに来たに違いないだろうけど…。声をかけてくれたらよかったのに」
そうしたら僕だってあんな面倒くさいことしなくてすんだんだよ。
なんてちょっとひどいことを言ってのける。
「はぁ…?!アンタ何言ってんスか!あんな状況の中出て行けるわけないじゃん!…それより先輩、彼女いるって聞かないのは好きな人がいたからなんスね」
誰なんスか。
あぁ…聞かなければよかった、と半ば弾みで口にした言葉に後悔する。
馬鹿じゃないのか、ホントに。
再びそう思った。
何で自ら傷つくようなまねをするのか。
ホント、ばかだ、よ。
そんなオレの様子に一瞬驚きの表情を見せた後、何か思案するように女の人のように細くて長くて綺麗な指を顎の下へと持っていき、目を伏せている。
睫毛が長いなぁ、なんてこの場に不釣合いなことを考える己の思考に苦笑する。
あぁ、もう、ホントに自分はこの人が好きなんだ。
そう思っていると不二先輩が顔を上げる。
その顔を見てオレは息を呑んで、そして、見惚れた。
だって、笑顔なんだ、今まで見たこともないような、そんな、綺麗な笑顔だった。
「…僕の好きな人ってね。黒髪で黒い瞳で、あ、ちょっと猫っ毛でつり目でさぁ…。プライドが高くて…本当に血統書つきの黒猫みたいなんだ」
「…」
可愛いんだよ。
なんて、愛おしそうに微笑む。
やっぱ聞かなきゃ良かった。
こんな幸せそうに他人のことを話す不二先輩なんて見たくなかった。
醜い嫉妬心だって解ってはいるけれど、でも、そう思わずにはいられなかった。
「でも僕はその子に好かれてる自信がないんだよね。嫌われてはないと思うんだけど。ねぇ…越前、僕はその子に想いを告げてもいいと思うかい?」
なんて残酷な人なんだろう。
オレの気持ちなんて知らないだろうけど。
でも、今のオレにはその言葉は投げかけてほしくなかった。
それでもオレは何もなかったように彼に言葉を返す。
「先輩なら…先輩なら誰でも落とせると思いますよ」
「そうかな」
「…はい」
うん、そっか、と微笑む不二先輩に今度こそオレは我慢の限界だった。
両手を握り締め、俯くオレを温かい何かが包み込むのを感じた。
ふと覚えのある香りが鼻を擽るのを感じ、驚いて顔を上げようとするとそれを制するかのようにさらに抱きしめられた。
あの、甘栗色の、想い人に。
「せっ…せんぱ」
「好きだよ」
「…っ」
行き成りのことに顔を真っ赤に染め上げ、うろたえるオレに再度彼は言う。
「好きだ、越前」
これでもかと言うほどの甘い声に酔ってしまいそうになる。
「…うそっ」
遊ばれているのではないかとそう言って彼の肩を押し返す。
でも、彼はそれを許してくれなかった。
「嘘じゃないよ」
「だって…オレも先輩も…」
「うん。わかってる。それでも僕は君が、越前リョーマっていう一人の人間が好きなんだ」
あまりの台詞に顔を上げると思ったよりも近くに不二先輩の顔があって驚いた。
しかし、よくよく見ると不二先輩の頬も微かだがオレと同様に朱に染まっているじゃないか。
「先輩…頬朱い」
「…」
「…心臓も速い、ね」
「…っ」
先輩の左胸に心音を聞くために耳をくっつけた。
「…当たり前でしょ。好きな子を抱きしめてるんだから」
しかも、一世一代の告白だよ。
なんて頬を赤らめてちょっと拗ねたように言うもんだから、なんだかおかしくて。
そんなオレに笑わないでよ、って恥ずかしそうに言う先輩をもう疑うことなんてできやしなかった。
「先輩…」
「ん?」
「オレも、オレも先輩が好きだよ」
「…っ」
かぁっと普段の先輩からは想像出来ないくらい頬を赤らめていた。
つられるようにしてオレの頬も朱に染まる。
そんな先輩ににっこり微笑みかけると彼も笑みを返してくれて、強く抱きしめてくれた。
「好きだよ」
どちらともなく言った言葉が綺麗に重なって、なんだか妙におかしくて、中庭には長い間オレと不二先輩の笑い声が響き渡っていた。
なんて、それはオレの気のせいなのかもしれないけれど。
恋とか、愛とか、そんなものじゃなくていいから、少しでも、少しだけでも、見ていてくれたら嬉しい、な。
Sweet colors
「好きです」
鈴のような可愛らしい声が人気の少ない、というより人気のない裏庭に響く。
此処が校内でも有名な告白スポットだなんて全く忘れていた。
そんな場所で、しかも死角になるような場所で昼寝をする自分も悪いが、回りを確認せずに告白劇をおっぱじめる彼女も悪い、と心の中で悪態をつく。
そんな一人の少女が頬を染めて一生懸命告白している相手は、自分のチームメイト兼先輩である甘栗色の髪と瞳を持つ笑顔を絶やさない『彼』だった。
告白を受けている今も微笑みを保ち続けている。
が、面倒くさいと言うのがありありと見て取れるほど今の彼を纏う空気が違うのだ。
彼らしくもない、どうかしたのだろうか。
そんな微妙にしか違わない彼の雰囲気を感じ取れるものなど殆どいないだろう。
大抵の者はあの笑顔に騙されるから。
それほど些細なものなのに、それに気づいてしまった自分がどれだけ彼を見ているのか再び認識させられる。
どれだけ見ていたって、どれだけ想っていたって、彼が振り向いてくれるだろう事はありえないというのに…。
馬鹿みたいだな、と思っていると甘栗色の彼が口を開いた。
「…ごめんね、僕は君の気持ちに応えてあげられない」
冷たい声だと思った。
表情は笑顔のままだったけれど、突き放すような、そんな、冷たい音だった。
「好きな人がいるんだ」
続けられた言葉に、自分に言われたわけではないというのに心に深く何かが突き刺さったような気がした。
その声は今までの中でも一番甘く響いていて。
その表情も比べ物にならないくらい甘くて切ないものだった。
本当に好きなんだ、と知りもしない彼の想い人に嫉妬の感情を覚える。
オレにはそんな権利ありはしないというのに。
自分の考えに没頭しすぎて、周りの状況がつかめていなかった。
だから、近づいてくる足音に気づけなかったのも仕方のないことだった。
「…覗きは良くないなぁ」
「…っ」
その声に慌てて振り向くと目の前に広がったのは甘栗色。
オレの想い人だった。
「ふっ…不二先輩っ!別に見たくて見てたわけじゃありません!」
本当に、見たくも聴きたくもなかったんだ。
顔を歪めてそう言うオレに不二先輩は小さくため息を吐いた。
そのため息に肩を揺らすオレに不二先輩は苦笑すると口を開いた。
「…越前、おおかたお昼寝でもしに来たに違いないだろうけど…。声をかけてくれたらよかったのに」
そうしたら僕だってあんな面倒くさいことしなくてすんだんだよ。
なんてちょっとひどいことを言ってのける。
「はぁ…?!アンタ何言ってんスか!あんな状況の中出て行けるわけないじゃん!…それより先輩、彼女いるって聞かないのは好きな人がいたからなんスね」
誰なんスか。
あぁ…聞かなければよかった、と半ば弾みで口にした言葉に後悔する。
馬鹿じゃないのか、ホントに。
再びそう思った。
何で自ら傷つくようなまねをするのか。
ホント、ばかだ、よ。
そんなオレの様子に一瞬驚きの表情を見せた後、何か思案するように女の人のように細くて長くて綺麗な指を顎の下へと持っていき、目を伏せている。
睫毛が長いなぁ、なんてこの場に不釣合いなことを考える己の思考に苦笑する。
あぁ、もう、ホントに自分はこの人が好きなんだ。
そう思っていると不二先輩が顔を上げる。
その顔を見てオレは息を呑んで、そして、見惚れた。
だって、笑顔なんだ、今まで見たこともないような、そんな、綺麗な笑顔だった。
「…僕の好きな人ってね。黒髪で黒い瞳で、あ、ちょっと猫っ毛でつり目でさぁ…。プライドが高くて…本当に血統書つきの黒猫みたいなんだ」
「…」
可愛いんだよ。
なんて、愛おしそうに微笑む。
やっぱ聞かなきゃ良かった。
こんな幸せそうに他人のことを話す不二先輩なんて見たくなかった。
醜い嫉妬心だって解ってはいるけれど、でも、そう思わずにはいられなかった。
「でも僕はその子に好かれてる自信がないんだよね。嫌われてはないと思うんだけど。ねぇ…越前、僕はその子に想いを告げてもいいと思うかい?」
なんて残酷な人なんだろう。
オレの気持ちなんて知らないだろうけど。
でも、今のオレにはその言葉は投げかけてほしくなかった。
それでもオレは何もなかったように彼に言葉を返す。
「先輩なら…先輩なら誰でも落とせると思いますよ」
「そうかな」
「…はい」
うん、そっか、と微笑む不二先輩に今度こそオレは我慢の限界だった。
両手を握り締め、俯くオレを温かい何かが包み込むのを感じた。
ふと覚えのある香りが鼻を擽るのを感じ、驚いて顔を上げようとするとそれを制するかのようにさらに抱きしめられた。
あの、甘栗色の、想い人に。
「せっ…せんぱ」
「好きだよ」
「…っ」
行き成りのことに顔を真っ赤に染め上げ、うろたえるオレに再度彼は言う。
「好きだ、越前」
これでもかと言うほどの甘い声に酔ってしまいそうになる。
「…うそっ」
遊ばれているのではないかとそう言って彼の肩を押し返す。
でも、彼はそれを許してくれなかった。
「嘘じゃないよ」
「だって…オレも先輩も…」
「うん。わかってる。それでも僕は君が、越前リョーマっていう一人の人間が好きなんだ」
あまりの台詞に顔を上げると思ったよりも近くに不二先輩の顔があって驚いた。
しかし、よくよく見ると不二先輩の頬も微かだがオレと同様に朱に染まっているじゃないか。
「先輩…頬朱い」
「…」
「…心臓も速い、ね」
「…っ」
先輩の左胸に心音を聞くために耳をくっつけた。
「…当たり前でしょ。好きな子を抱きしめてるんだから」
しかも、一世一代の告白だよ。
なんて頬を赤らめてちょっと拗ねたように言うもんだから、なんだかおかしくて。
そんなオレに笑わないでよ、って恥ずかしそうに言う先輩をもう疑うことなんてできやしなかった。
「先輩…」
「ん?」
「オレも、オレも先輩が好きだよ」
「…っ」
かぁっと普段の先輩からは想像出来ないくらい頬を赤らめていた。
つられるようにしてオレの頬も朱に染まる。
そんな先輩ににっこり微笑みかけると彼も笑みを返してくれて、強く抱きしめてくれた。
「好きだよ」
どちらともなく言った言葉が綺麗に重なって、なんだか妙におかしくて、中庭には長い間オレと不二先輩の笑い声が響き渡っていた。
PR
この記事にコメントする
忍者ブログ [PR]
